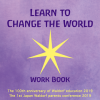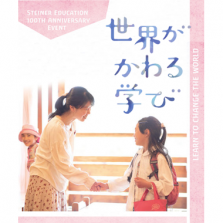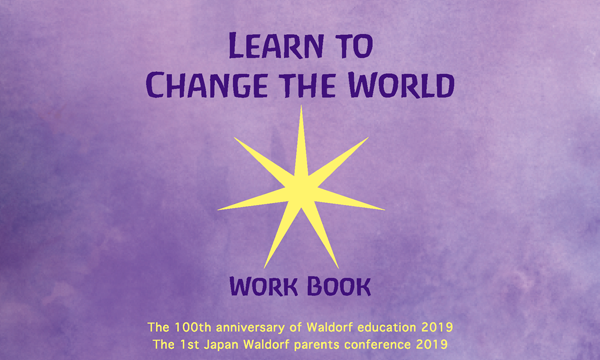
2019年9月15日(日)、100年を記念して全国のシュタイナー学校の保護者が東京賢治シュタイナー学校に集まりました。
世界の100年、日本の30余年の歴史を振り返りながら「いま」を考えるために、ワークブック『LEARN TO CHANGE THE WORLD』もこの集いのために制作されました。
全国の保護者たちは、このワークブックを手に、「自分と他者を知る」「社会とのつながり」「学校運営」「協働を目指して」「家庭環境」「卒業生との交流」「学童保育の可能性」というテーマ毎に集まり、お互いの知見と親交を深め、100周年にふさわしい実りを胸に帰途に就いたのでした。
“社会イニシアティブ”世界フォーラム
プロジェクトリーダーより
100周年記念保護者カンファレンスに贈られたメッセージの全文です。ワークブックには紙幅の関係で一部を割愛して掲載したものです。
ジョーン・スリー「生命体としてのヴァルドルフ学校」

ヴァルドルフ教育の基礎となる、一つの理解があります。それは人間の中にはある精神的な実質が備わっていて、それが社会的な人々のコミュニティーに受け入れられ、養育されたとき、そのユニークな個性が展開することができる、ということです。公教育の古典的な内容も申し分のないものですが、ヴァルドルフのアプローチは学習プロセスの中にアートの質を取り入れようとします。それによってすべての子どもの中に生まれつき備わっている創造性と想像力を刺激しようとするのです。年齢に応じたカリキュラムと方法論を通して、発達の変わりゆくフェーズに配慮することで、一人ひとりの子どもは、恐怖やプレッシャーによってではなく、興味を抱き、熱心に学習するための動機付けを得ます。これによって生涯にわたる学びの可能性が促進されます。ヴァルドルフ教育が目指しているのは、一人ひとりの個人としての子どもが社会的に目覚め、自分の文化的環境の中に自信をもって参入できるようにすることです。そこでは思考における自由、感情におけるバランス、行為における責任を発達させようとしています。
第一次世界大戦の終結の後、ヨーロッパと周辺世界の社会には、社会的、経済的、人間的レベルでの強い苦しみと混乱がもたらされました。ヴァルドルフ・アストリア煙草工場のオーナーであったエミール・モルトは、この過酷な状況に応答するために学校を創立し、根本的に新しい社会秩序を促進する力をもった生徒たちを育てようとしました。彼は自分の労働者の子どもたちのための学校の教育監督となることをルドルフ・シュタイナーに依頼しました。社会におけるいかなる変革も、子どもたちの教育から始めるのが一番よいことに気づいていたからです。ルドルフ・シュタイナーはこの挑戦を引き受け、1919年9月、この種のものとしては最初の学校を開校しました。そして、教育へのこのホリスティックなアプローチは一つの文化的な出来事であり、「宇宙的な秩序の祝祭」 だと述べました。
そのため、ヴァルドルフ教育のユニークな特徴は、変わりゆく文明の中で新しい社会的能力を形成、育成しようとしていることにあるといえます。最初の中心的な特徴は、人間は身体的、社会的、精神的存在であるという理解が、カリキュラムの核心になっていることです。第二に、社会的な気づきと変革のための教育であるということです。社会的行為としての教育は、大人になって労働生活に参加するとき、細やかな感性と柔軟性、他者への共感、そして環境全体への深い関心と愛を備えているための基盤をつくるということです。第三のキー・エレメントは、教育への芸術的なアプローチです。これはストレスと神経の消耗に対抗するために、想像力と創造的な学びという生涯にわたるプロセスを促進するということです。
このような教育へのアプローチは、21世紀の増大するニーズや挑戦に向き合う可能性を備えています。ヴァルドルフ学校は、それぞれが生命体であり、個人の自由、権利の平等、アソシアチブな経済という社会有機体三分節化の特性を取り入れることで、高まりつつある人間の尊厳や地球の健康への気づきに寄与するものです。
ジョーン・スリー
2019年7月
ウテ・クレーマー
「2つの素晴らしい誕生日を祝う年」

2019年という年は、2つの素晴らしい誕生日を祝う年です。一つは社会有機体の三分節化運動、もう一つはヴァルドルフ教育、それらが生まれて今年は100年となる年なのです。この二つのできごとは、お互いに関係のあることでしょうか?
ええ、まさにその通りなのです!
社会三分節化運動なしに人間的な教育学はなく、自由な教育と文化の生活なしに社会三分節化運動もありえません。その二つが補いあってこそ、「平和文化の創造」が可能となるのです。シュタイナーは、第一次世界大戦という唯物主義の集大成のような大惨事を目の当たりにしたとき、そのことに気づきました。平和のための教育と三分節化した社会の構築という二つの課題の間の、この本質的なつながりを理解することは、それからの100年間にわたって、とても大切なことでした。人智学者だけでなく地上のすべての人にとってたいせつなことではありましたが、シュタイナーの実践的な知恵にアクセスすることのできた人智学者にとってはなおさらです。100年前、人智学者には特別な課題が与えられました。他の様々な世界観、他の様々な社会観、現代科学の研究、そして社会を変えるための他の様々な運動に対して自分を開き、それらと力を合わせていくことです。そんな行動の例が、例えばELIANTという市民運動です(P.26)。EU議会にまで働きかけて、より人間的な社会を作るためのアドボカシーをしています。もう一つの例は、子ども時代のためのアライアンスです(P.22)。子ども時代を守るという使命のために、ヴァルドルフ運動の枠を超えて活動しています。あるいは、ユネスコスクールのネットワークです(P.30)。人智学ととてもよく共通した方向を目指していると言えるでしょう。
21世紀を生きる私たちの課題は、人間の本質の中で自分自身を深めることであると同時に、他の人たちと力をあわせることにあります。視野と行動を広げるのです!
子どもたち、若者たち、そして大人たちも、私たちに深い問いを投げかけます。その問いの前に、私たちはときに無力感におそわれます。その無力感に耐え、前を向いて歩くことをあきらめないためには、たくさんの自己教育が必要です。例えば、生まれたばかりの子どもを観察してみましょう。その視線の中に、何を見ることができるでしょうか。赤ちゃんは目を見開いて「あなたは、私をこの世界にどのように迎え入れてくれるのですか? 大地にも魂にも命がなく、こんなに破壊されてしまったこの世界に?」と問うているようです。「私はあなたたちを助けるためにやってきたのですよ。霊界からの最新ニュースを伝えるために。でも、そのためには、まずあなたたちが私を迎えてくれないといけません。何年も何年も、たっぷりと私の世話をしてくれないといけないのです」。
確かに、私たちはときに無力を感じます。しかし勇気と自信を育てることがでるはずです。大天使ミカエルが助けてくれるからです。私たちは誰も、生まれてくる前にある霊的な領域を通り、人間が人間を信じるための、決してあきらめない勇気と信頼をミカエルから与えられています。そのためには、まず私たちが一歩を踏み出さないといけません。天秤の皿に、自分の小石を置くのです。その小石は、自分のいる場所でできることという小石です。でも、地球のことを考えながらおこなう行為です。
大切なことをまとめてみましょう。
- 自由:一人一人違う個の、自由で個別な発達のために他の運動と一緒に闘うこと
- 平等:自分が自分であること(例えば移民として、例えば同性愛者としての自分)の権利を尊重し、法律で保障すること
- 友愛:誰もが自分のニーズを満たすことができるように、生き残るためだけでなく、生きるために働くこと
ウテ・クレーマー
2019年7月
カンファレンス参加者の皆様:以下にワークブックの正誤表と補足があります。アイコンをクリックしてご覧下さい。